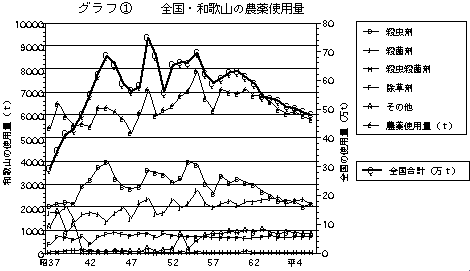白坂雅子(京都大学農学部農学科四回生)
1. はじめに
昨年から池田さんとともに打ち込んできた 「農薬要覧(植物防疫協会)」からのデータをまとめたものです。ただし、これは出荷量のデータなので、例えば使い残した農薬を翌年に持ち越すこともあり、実際の使用量とは多少のずれがあるものと思われますが、ここでは使用量として話を進めていきたいと思います。
2. 全国の使用量について
急激に増えていた使用量は、1969年でいったん減少、1974年を最高にして、また徐々に減ってきています(グラフ①)。
この間にどんなことがおきていたのでしょうか。1968年から1973年にかけて、Hg剤 、BHC、DDTと相次いで使用禁止となりました。また、1974のオイルショックではその後しばらくの間、農薬の生産自体がままならなかったようです。この様な社会的な影響以外に、その年の気候状態というものが農薬をまく回数、量にかなり影響してくるようです。「日本農業年鑑」に”冷害のため、農薬使用量が減る”という記述が何度も出てきており、農薬ゼミの先輩である、美山さんの助言によるエルニーニョの発生した年(つまり冷害の年)、1976~77、1982~83とグラフの下がりは一致しています。ここで、なぜ冷害になると農薬の使用量が減るのか、という疑問が出てくるのですが、これは冷害になると生産者の意欲が落ちてしまって、後をまかなくなってしまうためだと思われます。
3. 和歌山県の使用量について
県全体の使用量は、全国のものとほぼ同じ動きをしています。その下の五つのグラフはその内訳を示しています。これを見ますと、殺虫剤、殺菌剤でそのほとんどを占めています。除草剤は、その出現によって労働時間が大幅に短縮されたと言われていますが、30年間、ほぼ一定の量を保っています。殺虫剤と殺菌剤をいっぺんにまいてしまおうという殺虫殺菌剤も、農薬全体からすればごくわずかを占めているにすぎません。
次に、1966、67、88、92年の、和歌山または下津町に出された温州みかんの防除歴にのっていた農薬について抜き出しました。防除歴というのは、農家に対していつ頃どんな農薬をどれくらいまけばよいかを示したものですから、これにのっているものが全てまかれたとは限りませんし、実際、1967の防除歴にのっていたBINAPACRYL(アクリシッド)水和剤というダニ剤は、和歌山では全く使われていません。また、1967~88の20年間の防除歴というものを見ていないので、この間だけ使われていたような農薬については、調べることができませんでした。
<殺虫剤>
このほとんどをマシン油乳剤が占めています。これは炭水化物の混合物で自然物、毒性も普通、魚毒性もAと、かなり安全と言えるからか、昔からかなりの量がまかれています。ダニやカイガラムシなどの表面に散布して窒息させて殺すというものです。このマシン油にもいろいろあり、ここで抜き出したうちのPAPマシン油、エチオンマシン油のように、マシン油に他の農薬を加えたものも多いようです。このマシン油を除いた他の殺虫剤について、防除歴などからその主な対象害虫によって、ダニ類、カイガラムシ類に分けました。
<ダニ類>
まず注目してほしいのが、MNFA(ニッソール)乳剤です(グラフ②)。
松本悟さんが中毒し、農薬裁判のきっかけとなった農薬です。1965~73にぱっと出てきて消えていきました。このニッソールと後述するフッソールは、ともにフッ素系の農薬でこれらは有機リン系の農薬にとってかわられていきます。この有機リン系農薬に、アセフェート(オルトラン)水和剤があります。これは、ダニ類の他にチャノキイロアザミウマといって、1987頃からかんきつの重要害虫になってきた虫にもつかわれています。このオルトランの伸びは、チャノキイロアザミウマの出現によるところも大きいと思われます。また、CPCBS(ネオサッピラン)水和剤は、ハダニ類の殺卵、殺幼虫に使われますが、発生初期に予防に使うなど、散布時期が限られていて使いにくかったのか、1970年代には消えていきます。
<カイガラムシ類>
モノフルオル酢酸アミド(フッソール)液剤、先ほどのニッソールと同様に1960年代に盛んに使われ、1974には消えていきます。(グラフ③)
そしてここでもまた、PAP(エルサン)乳剤、DMTP(スプラサイド)乳剤などの有機リン剤が、その後を引き継いでいきます。
また、一緒にグラフにのせているBHC塗布剤(ネオサッチュウコート)は、天牛すなわちカミキリムシに使われていたものです。このBHCは、有機塩素系農薬の販売の禁止及び制限を定める省令の改正(1971/11/30)によって登録が失効となっており、現在は使われていません。今、省農薬ミカン園では見つけたら首をひねって殺すという防除しか行っていないので、カミキリムシに対する農薬があったというのは意外でした。
<殺菌剤>
石灰硫黄合剤がほとんどを占めています。(グラフ④)
これはそうか病に対して使われますが、ハダニやヤノネカイガラムシなどに対して殺虫剤としても使われます。また、1970頃から増えてきているマンゼブ(ジマンダイセン)水和剤、マンネブ(エムダイファー)水和剤は、黒点病に対して使われます。この黒点病は大変な病気らしいのですが、なぜか仲田園には出てきません。殺菌剤はこれら三つの硫黄殺菌剤でほとんどを占められています。また、使用禁止となった Hg剤、銅・水銀水和剤(フミロンボルドー)は、1967には姿を消します。
このように、個々の農薬についてみてみますと、時代の移り変わりにともなって農薬も移り変わっています。殺虫剤において、フッ素系のものから有機リン系のものへと移ってきたことが分かります。また、BHC剤、Hg剤などのように使用禁止となったものもあります。現在使われている農薬が、もう、数年後には他の農薬にとって変わられているかもしれません。私達が打ち込んだ農薬要覧の中にも、全く使われていないものも含めて、ものすごい量の農薬が登録されています。
4. みかん生産と農薬
それでは実際にみかんを作るうえでの農薬の使用は、どう変わってきたのでしょうか。和歌山県全体での農薬使用量は、ここ15年くらい徐々に減りつつあります。しかし、同時にみかんの生産面積というものも減ってきているわけで、単位面積当たりの使用量を出してみると、結局増えていることになります。しかし、これだけでは、農薬の毒性を低くした結果、使用量が増えたという可能性も出てくるので、農薬にかかったお金というものもみてみますと、消費者物価指数で補正してもなお、増えてきていることが分かります。
5. おわりに
この内容を1996/2/9のゼミで発表するにあたって、農薬研の津田先生にお話をうかがいました。その時の話では、農薬の使用は全体的な動きとしては、減少の方向へ向かっているだろうということでした。その理由としては、生産者の意欲が減ってきていること、または篤農家の人々が農薬を減らす方向に進んでいること、農薬自体が殺虫殺菌剤のように合剤化してきたこと、などを挙げていました。しかし、先程見たように和歌山のみかん生産において、その単位面積当たりの使用量も農薬代も増えてきています。安全を求めるなら農薬は使わない方がいいと分かっていても、まだまだ使わざるを得ないのが現状なのではないか、と感じました。